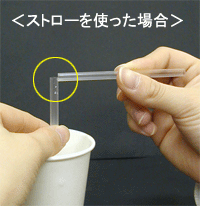| 特長 |
- 身近なものから簡単に霧吹きができる。
- ガラス細工の初歩として、またベルヌーイの定理の説明に使える。さらに、製作した霧吹きで人工の虹を作ることができるので、光の単元の興味づけとしても効果がある。
- 身近な道具の原理と、それを発明した先人の偉大さにも気付かせることもできる。
|
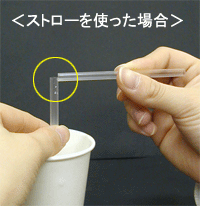 |
| 用具 |
ビーカー、ガラス管2本(内径6mm、内径2mm)、やすり、ガスバーナー、紙コップ、水
なければストロー2本でも対応できる。
|
| 方法 |
- ガラス管の適当な長さのところで、やすりで傷をつけると簡単に割れる。内径の小さいほうは長さ10cmくらいがよい。ガラス管の両端は、そのままでは危険なので、バーナーの炎に当てて、丸みをつける。体験としてこれらの過程を生徒にやらせてみるのも教育効果が大きい。
- 写真(ストローでやった場合)のように2本を持ち、コップにつけていない一方から吹くと霧吹きができる。これはガラス管でやった場合も同様である。
- 太陽を背にして吹くと人工の虹ができる。光の単元の導入やまとめの実験として行い、虹の原理を説明するとよい。
|
| メモ |
- 写真のように上のストローの口を半分ふさぐように下のストローを持つとうまくいきやすい。
- ガラス管の太さや長さ、あるいは吹く強さを変えて実験し、ベルヌーイの定理を学習することもできる。
- あらためて市販の霧吹きをよく観察すると、いろいろな工夫がされていることが分かる。霧吹きは流体力学がまだ知られていない時代からあったが、これを発明した先人の偉大さに感心するであろう。
|